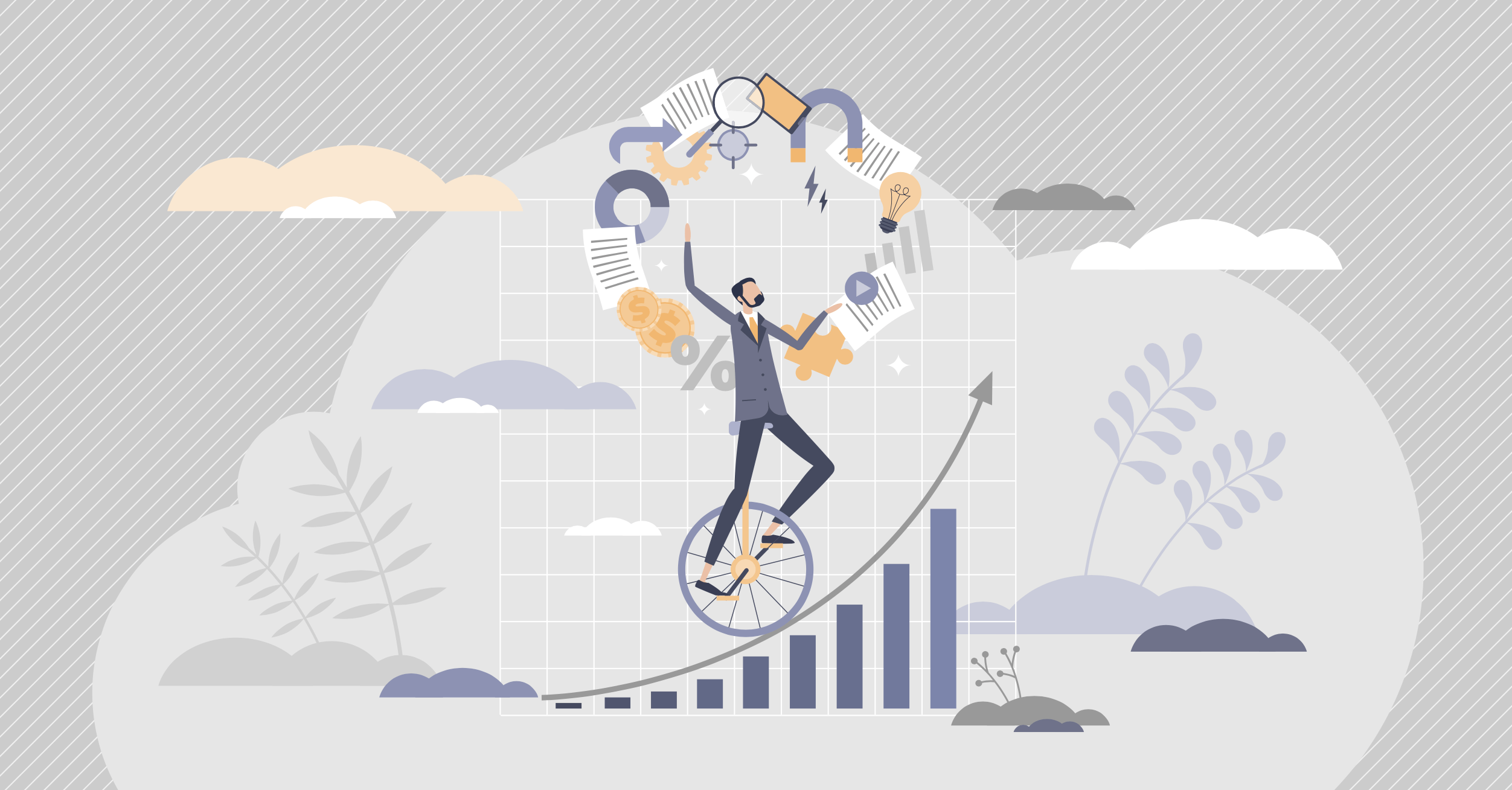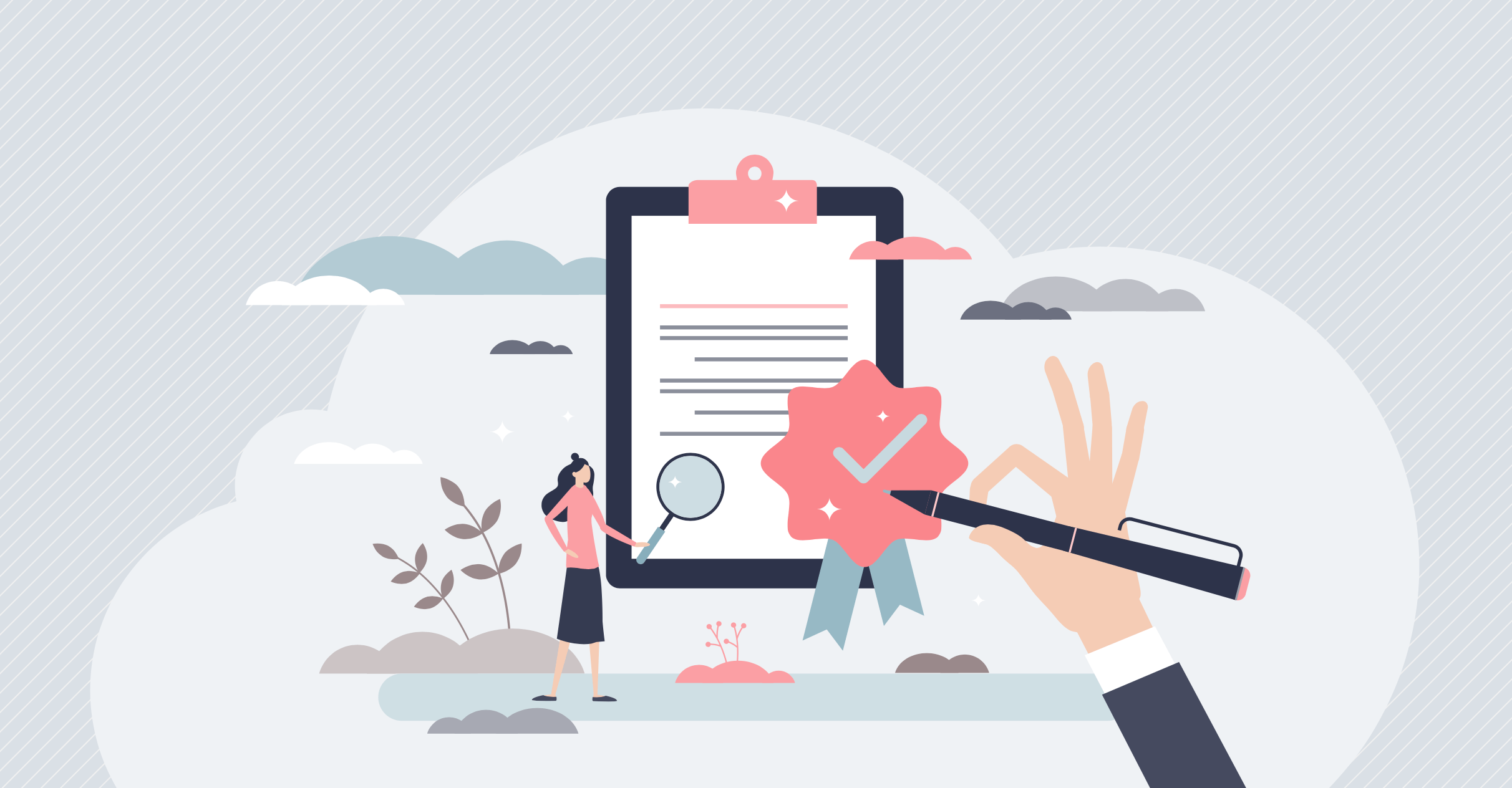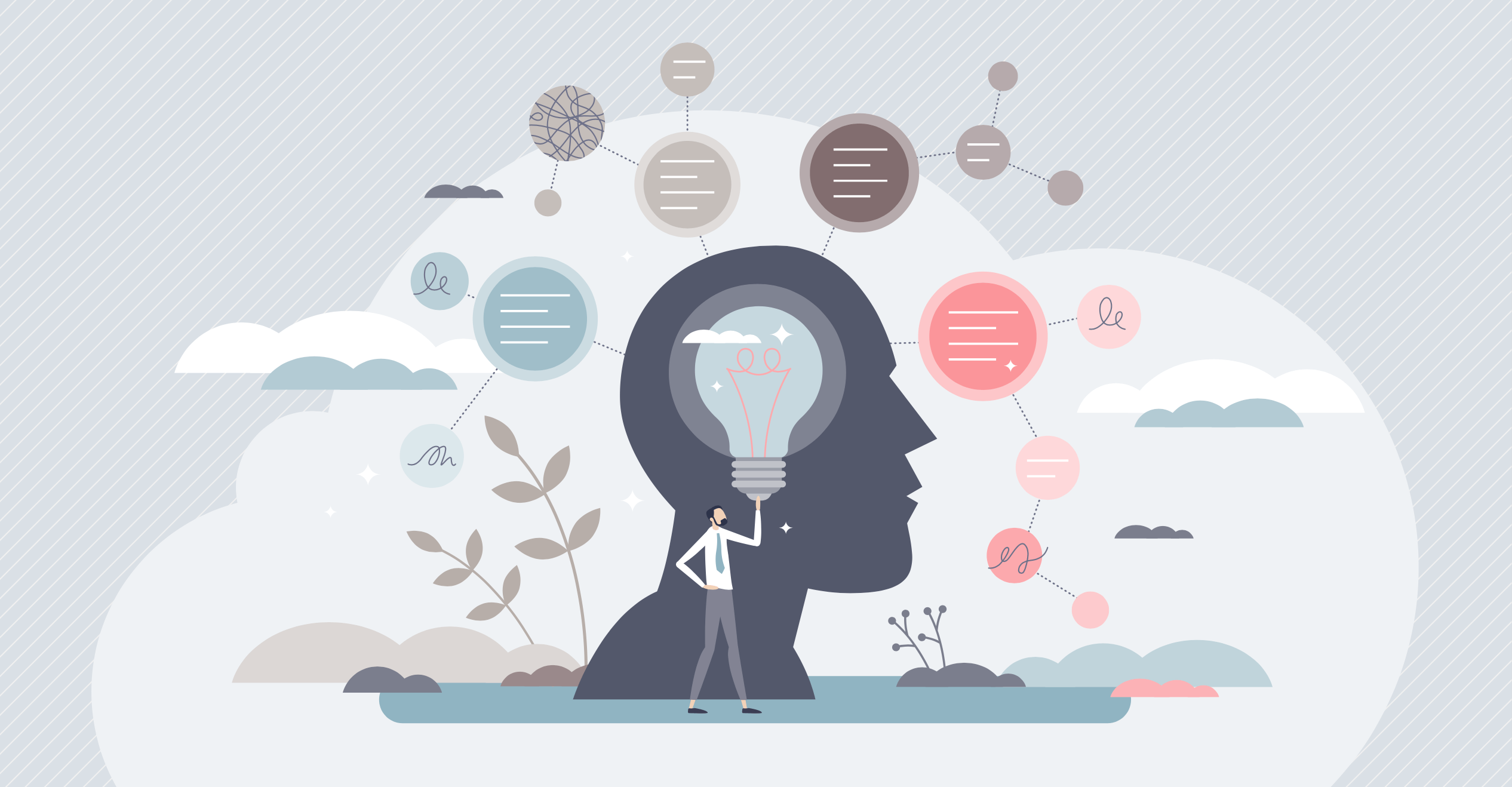退職や異動の際に後任の方や残された人たちが困らないように引き継ぎをしっかり行うことが大切です。
引き継ぎをしっかり行うことで後任者も安心ですし、前任者も次のステージに心おきなく行くことが出来ます。
引き継ぎを失敗しないためにも引き継ぎマニュアル資料を作成しましょう。
今回は、引き継ぎマニュアルの作成ポイント を分かりやすくまとめてみましたので参考にして完璧な引き継ぎを目指していきましょう。
 後任者がすでに決まっている場合は1、2週間前に実際に一緒に業務を行い引き継ぎを行いましょう。
完璧な引き継ぎマニュアルを作成出来たとしても一緒に仕事をしながらわからない事はないかを確認しておくとより完璧に引き継ぎを行うことが出来、後任者も安心出来ます。
後任者がすでに決まっている場合は1、2週間前に実際に一緒に業務を行い引き継ぎを行いましょう。
完璧な引き継ぎマニュアルを作成出来たとしても一緒に仕事をしながらわからない事はないかを確認しておくとより完璧に引き継ぎを行うことが出来、後任者も安心出来ます。
引き継ぎ資料マニュアルを作るタイミングは?
マニュアルを作成することはある程度な時間を費やします。 ギリギリに慌てて作り始めても抜けや漏れが生じてしまう可能性があります。 退職や異動日が決定したその日から作成を開始し、日々行っている業務を逐一内容を含め記入していく ことをおすすめします。 退職直前に頭の中でまとめただけだと万全なマニュアルは完成しません。 業務はその都度書き出し中途半端な内容で終わらないように自分が会社を去ることが決定した日からマニュアル作成を始めましょう。引き継ぎに失敗しないための3つのマニュアル
全体を把握出来る様な時系列マニュアル
まず、いつどんな業務を行っているのか全体を把握できるような資料を作成しましょう。 いつ頃どのくらいの期間で行うものなのか? 年間スケジュール、月間スケジュール、週間スケジュール(必要であれば)で分けて作成しましょう。 業務を箇条書きで書き出しやる事や内容を簡潔にわかりやすい言葉で表示しておくと分かりやすいと思います。 エクセル表を使って作成していきましょう。 内容補足や締め切りの情報も補足しておくといいですね。 『担当の業務の洗い出し』に関してはこちらの記事で注意点など詳しくご紹介しているので、合わせてお読みくださいませ。 【知らないと絶対失敗する!?】引き継ぎ時の担当業務の洗い出し《4つのステップ》誰が見ても同じ業務が出来るようなわかりやすいマニュアル
後任者や他の職員がみても同じように仕事が出来るように作成してください。- 業務の目的を明確に記入(目的や意図など)
- 作業手順を記載
データ保管場所一覧表の作成
異動や退職後に良く起こるのが資料やデータの保管場所が分からなくなるという事です。 あのデータどこに保存してある?あの資料はどこ?など後から連絡を受けることにもなりかねませんし、後任者も探すのに無駄な時間を費やしてしまいます。 そのようなことにならない為にもデータ保管場所一覧表を作成しましょう。 一覧表の項目-
- 資料名
- ジャンル
- データor書類
- 保存先
実際に後任者と一緒に仕事を行いましょう
 後任者がすでに決まっている場合は1、2週間前に実際に一緒に業務を行い引き継ぎを行いましょう。
完璧な引き継ぎマニュアルを作成出来たとしても一緒に仕事をしながらわからない事はないかを確認しておくとより完璧に引き継ぎを行うことが出来、後任者も安心出来ます。
後任者がすでに決まっている場合は1、2週間前に実際に一緒に業務を行い引き継ぎを行いましょう。
完璧な引き継ぎマニュアルを作成出来たとしても一緒に仕事をしながらわからない事はないかを確認しておくとより完璧に引き継ぎを行うことが出来、後任者も安心出来ます。